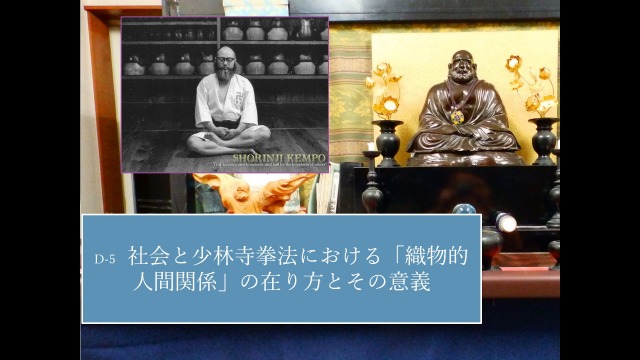
今日は、テーマ番号D-5の『社会と少林寺拳法における「織物的人間関係」の在り方とその意義』という1月23日に行なう、次の県教区本山認定研修会での講義内容を考えています。武専の派遣も12月には茨城の担当がありますし、労働局からの依頼の講演や小教区の認定研修会やらと立て続けに予定が続いているので、常に並行して思いついたことを書き留めるのが私の勉強スタイルです。
このタイトルを通して皆さんに学んでいただきたいことを伝えるのにと、頭に浮かんできたのが、このお話です。
筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう、略称: ALS)になってしまった拳士仲間を当時の少林寺の機関誌で取り上げてもらったが、励ましや、応援の手紙も来なかったと道院長講習会に参加した際に新潟の先生から聞かされ、機関誌の記事にあまり熱心に目を通していなかったことを恥じながら、手紙を書いたことを思い出します。
お礼の返信とともに送られてきたのは、一枚の署名用紙でした。当時、ALSの患者さんは深夜、就寝時に溜まる痰の除去は看護師か家族が行うしかなかったのですが、自宅で療養する場合、家族の負担が非常に大きく、これをヘルパーにも行うことを認めてほしいという内容の署名だったのです。
「この一枚を埋めて返すだけでいいのか!!」
そう思った、私たちは何人かで街頭に立ち署名を集め、道院では拳士や家族の皆さんにお願いし、周囲の自治会、学校や職場、様々な協力を経てとてつもない署名を集めて段ボールに入れて何箱も送ったのです。送った拳士から署名活動をしていた日本ALS協会に送られ、それまで不調だった署名活動に、とてつもない署名が他の団体の皆さんの力で集められ送られてきましたと、大喜びでホームページに署名の山を映した画像入りで、お礼の言葉が掲載されていました。そして、法案はつくられたのです。
武専の教員として初めて新潟に派遣された際、冒頭の挨拶でその時のお話をしました。それまでは、どこから来た先生だろう?と初めて見る私に、よそよそしい感じだったのが、講師紹介を終えると皆さんが寄ってきて、「あの時の先生だったんですね!!こんなうれしいことはない!!」と大騒ぎになってしまったのです。講義の中で、普段、私たちの行っている献血推進活動のお話をしたのですが、二度目に講師として伺った際に、皆さんからグループになって献血に定期的に行くようにしているという話を聞かせてくれたのです。とてもうれしい気持ちで一杯になりながら、その日も楽しい武専になりました。
私たちの自他共楽の精神は「ともに少林寺拳法を楽しむ」というだけのものではないのです。
自分の感じたことを周囲に伝える人がいたからこそ、気が付き反省し、それに応える者が生まれる、何に困っているのかを伝えたからこそ、その思いを共有し、何とかしようと努力が始まる。思いは広がり多くの賛同を集め、支える力を作り出す。私たちは理想境の建設に邁進すと唱えているように、そのために必要なのは常に時事に関心を持ち、問題意識を持ち、有志となって社会を支えることに鍛えた力を使える人間にならなければならないのです、開祖は
「愛だけでは世の中は決してよくなりません、自分を捨ててでも正しいものを助けるという力を養うことが大切なのです。…
少林寺拳法の拳士は一人残らず正義の勇者であれ!! 」
1972年鏡開き式 より
と我々に説かれていました。
常に、その精神をもって、周囲に協力し合える力の輪を広げていきましょう。


 15人
15人